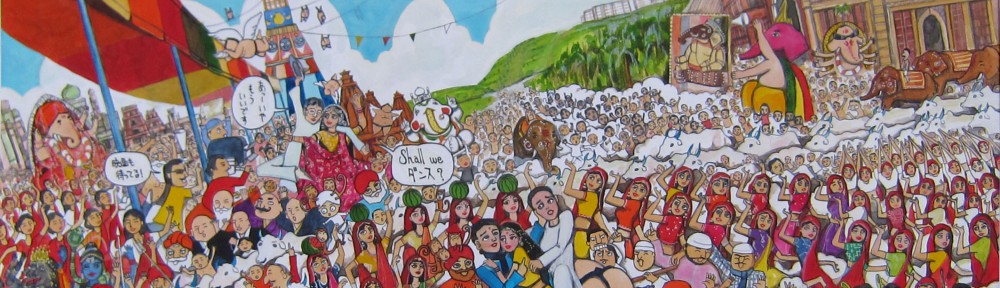昨日は今、話題になっている特別展『本阿弥光悦の大宇宙』に行ってまいりました。
話題になっている、というのは素晴らしいという声はもちろんですが、よくわからなかったという声も多々ある、という意味です。
先日見に行ったサントリー美術館「四百年遠忌記念特別展 大名茶人 織田有楽斎」展が、ド地味でド渋の展覧会だったので(ほめてます)、行く前に同じようなイメージを持っていました。
ところが実際に会場で目にしたものは絢爛豪華な桃山文化の粋でした。
刀剣や書というのは、絵画や彫刻といったものに比べて、最初は退屈さを感じるものですが、数を見ていううちに何となく善し悪しが見えてくるもの。
私もこの方面は素人同然ですが、職業柄、一般の人よりは書も刀剣も数だけは見ています。 ど素人の感想になりますが、まず刀剣において驚かされたのが保存の良さです。
ど素人の感想になりますが、まず刀剣において驚かされたのが保存の良さです。
鎌倉時代の刀剣なのに、ついさっき焼き入れされたような輝きがあるのにびっくり!
もちろん本阿弥家は刀剣の鑑定や研ぎを行う家系ですから、鎌倉時代の刀がそのままの形で残っていたわけではありません。何度も刀剣のメンテナンスがされていたでしょうが、鎌倉時代から令和の世までそれが続けられていたのが驚きです。
本阿弥光悦が生まれたのが1558年ですから、まさに世は戦国時代真っ只中。
命のやりとりをする道具を扱う家系から生まれた光悦が、美の鑑定をするというのは、それこそ命がけだったのでしょうか。
いやいや、それにしては光悦の求めた美はおおらかであるし、絢爛豪華でもある。
圧巻は俵屋宗達が下絵を描き、そこに光悦が三十六歌仙の和歌を書した『鶴下絵三十六歌和歌巻』です。
さらに見どころは光悦自身が作ったとされる陶器でしょう。
楽茶碗の楽家とかかわりの深かった光悦は、そのスタイルで陶器を作っていて、ここではそれらが展示されていました。
一子相伝の楽家当代(ここでは長次郎と道入)が焼いた完成度の高いものとは違い、光悦のそれは形もでこぼこしてるし、もう少しゆるやかでした。
楽家の当代たちが焼いた厳しい仕事とちがって、なんとなくユルい(本当はどうかわかりませんが)感じ…私はこちらの方が好きかな。