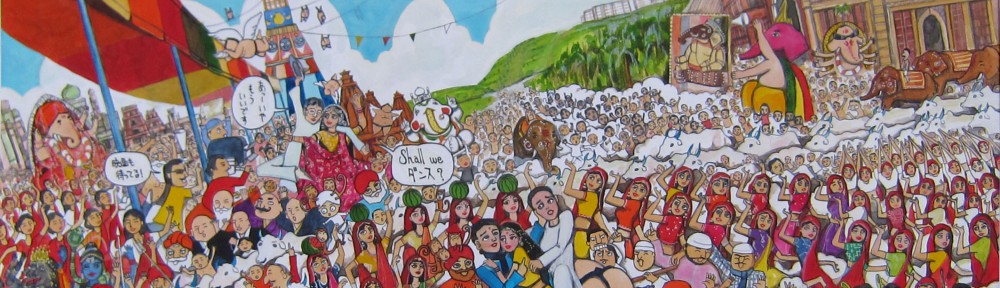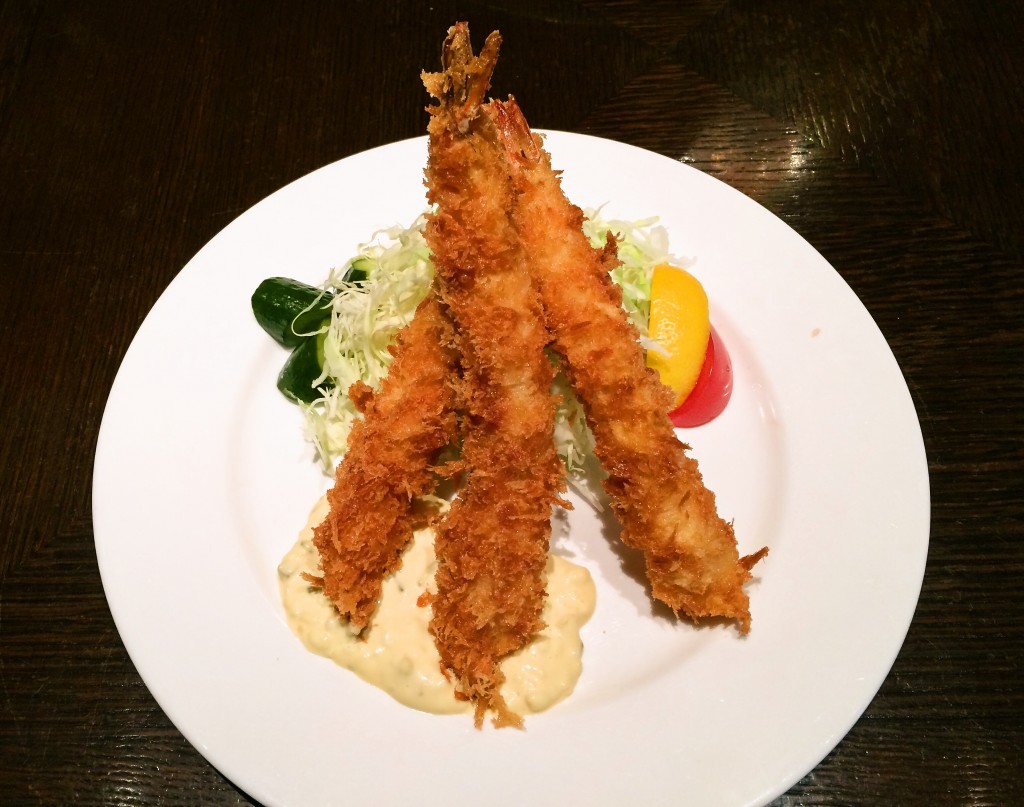ひょんなことから友だちからドラティ指揮のハイドン交響曲全集をいただき、仕事の合間に聞いてます。
ハイドンといえば学校の音楽室に貼ってある年表に「交響曲の父」と書かれている、文字通りの祖(ところでバッハは『音楽の父』、ヘンデルは『音楽の母』とされていて、私は最初、ヘンデルは女性だと思ってました)。
生涯書いたシンフォニーは108曲、10月に聞きはじめて、ようやく100番「軍隊」まで到達しました。
四十路を過ぎるとハイドンの良さがわかると良い、あの吉田秀和先生も大好きだったというハイドン。若い頃は退屈だと思っていたハイドンですが、四十路どころか五十路を過ぎて、しみいるようにハイドンが良いと感じるようになりました。
とはいえ、最初に書かれた初期のものは本当に退屈で、一度聞けば十分という感じで、どれも同じように聞こえます。これはモーツァルトのシンフォニーでも同じことですが、41番まであるモーツァルトに対して、ハイドンの交響曲は全部で108曲!
70番くらいまでは、まったく惰性のBGMとして聞いていたのですが、80番あたりから曲の輪郭がハッキリわかるようになってきます。
94番は有名な「驚愕」。
曲のタイトルにもなった、2楽章のド、ド、ミ、ミ、ソ、ソ、ミーの平凡なメロディは、こんなんで昔の人はびっくりしたんかと思うくらいですが、この平明な曲想が何とも言えません。
文字通り眠くなるようなメロディと、びっくり音はちょっとした曲全体のアクセントになっています。
それにしても驚いたのは、108ものシンフォニーを続けて聞くと、ハイドンの進化というのが如実に伺え、さらにハイドンの進化イコール音楽の歴史だということです。
バッハが完成させた平均律の12音は、ハイドンによってモーツアルトやベートーベンに受け継がれていったわけですが、その後継者たちの音楽の礎がハイドンの交響曲の中にあるのですね。
モーツアルトのジュピター交響曲の終楽章の「ド・レ・ファミ」や、ベートーベンの5番の動機も、ハイドン抜きには考えられません。
なんでもハイドンは、けっこうな恐妻家だったそうで、奥さんはハイドンがいっぱい曲を書いてお金を稼ぐと機嫌が良かったなんて話もありますが、仕事って、いっぱいやると何かができるという典型なようです。
あとCD2枚ほどでハイドンのシンフォニー制覇。
今度はカルテットでも聞いてみよっと♪
ハイドンは良いドン!・・・なんて、ウフッ♪